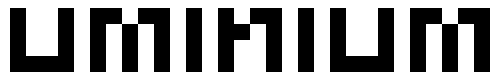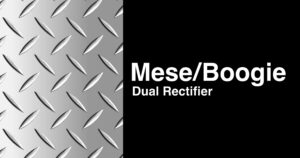日本でスタジオに入ったらほぼ必ずあるJCM900。
初めて触った真空管アンプがこれという方も多いのではないでしょうか。
90年代のロックシーンを語る上で欠かせないMarshallサウンド。
その中でも、一際モダンで攻撃的なサウンドで時代を築き上げたアンプが『Marshall JCM900』です。
伝説的なJCM800の後継機として華々しく登場し、時には賛否両論を巻き起こしながらもそのパワフルなサウンドで数多くのギタリストに愛されてきました。
この記事ではそんなJCM900の魅力と実力、歴史的背景から現代のデジタルシーンでの活用法、そして「なぜ日本のスタジオの定番なのか?」についてもお伝えします。
「よく見るけど詳しいこと知らないなぁ…」
そんな名機を端的に知って、より楽しむための試みです。
JCM900の概要
Marshall JCM900は、輝かしい歴史を持つJCM800の後継モデルとして1990年に発表されたギターアンプです。80年代後半から隆盛を極めたハードロックやヘヴィメタルのシーンでは、ギタリストたちがより強い歪みを求めていました。JCM800を改造する「モディファイ」が流行する中、そのニーズに真正面から応える形で、メーカー自身がハイゲインサウンドを標準搭載したのがこのJCM900です。
最大の特徴は、JCM800よりも深く、そして滑らかな歪みを生み出すプリアンプセクションにあります。特に「4100」に代表されるデュアル・リバーブ・モデルは、クリーン/リードの2チャンネル仕様で、フットスイッチによる切り替えが可能です。これにより、ライブ中にクリーンサウンドとハイゲインサウンドを瞬時に使い分けることができ、多くのギタリストから絶大な支持を得ました。
そのサウンドは、90年代の音楽シーンを象徴するものであり、ハードロック、ヘヴィメタルはもちろんのこと、グランジ、オルタナティブ・ロック、ポップパンクといった、よりモダンなジャンルのギタリストたちにも愛用されました。
JCM900にまつわるエピソード
JCM900の登場は、当時のギタリストたちの渇望に対するMarshall社からの回答でした。
80年代のヒーロー達はこぞってJCM800のゲインをブースターで押し上げたり、アンプ自体を改造したりしてより過激なディストーションサウンドを追求していました。この「ホットロッド(改造)マーシャル」のサウンドをメーカー純正でしかもより安定した品質で提供しようというコンセプトからJCM900は生まれます。
そのハイゲインサウンドを実現するためにプリアンプにダイオードクリッピング回路(半導体による歪み)を採用したことは、当時のギタリストたちの間で大きな議論を呼びました。「これは純粋なチューブサウンドではない」という批判的な意見も少なくありませんでした。それまでのMarshallアンプが、パワー管をフルドライブさせた際の豪快な歪みを信条としていたため、JCM900のモダンでタイトな歪みは異端と見なされることもあったのです。
ですが、時代はこの新しいサウンドを歓迎しました。特に、クリーンとリードを明確に使い分けることができ、エフェクトループも標準装備するなど、現代的な使用環境への対応力はJCM800を凌駕していました。結果的に批判を乗り越え新しい世代のヒーローたちに選ばれることになります。JCM900は伝統と革新の狭間で生まれ90年代という新しい時代のロックサウンドを定義した重要な一台と言えるでしょう。
JCM900と一緒に使われる機材
JCM900のポテンシャルを最大限に引き出す、定番の組み合わせをご紹介します。
キャビネット
- Marshall 1960A / 1960B
これぞ王道中の王道。
Celestion社製の「G12T-75」スピーカーを搭載したモデルとの組み合わせは、JCM900のタイトな高域とパワフルな中低域を余すことなく再生し、多くのレコーディングやステージで使われてきました。
コンパクトエフェクター
- オーバードライブ / ブースター
- Ibanez TS9 / TS808 Tube Screamer
ゲインをゼロ近く、レベルを最大に設定してJCM900をブーストするのは定番のテクニック。
音の輪郭がはっきりし、よりタイトで攻撃的なディストーションサウンドになります。 - Boss SD-1 SUPER OverDrive
TS系と同様に、ブースターとしての使用が非常に人気です。中域に独特の粘りを加えることができます。
- Ibanez TS9 / TS808 Tube Screamer
- ノイズサプレッサー
- Boss NS-2 Noise Suppressor
ハイゲインアンプの宿命であるノイズを抑制するための必需品。
特に深い歪みサウンドを作る際には欠かせません。
- Boss NS-2 Noise Suppressor
- 空間系エフェクター
- Boss DDシリーズ (Digital Delay)
JCM900はセンド/リターン端子を備えているため、クリアなディレイサウンドを得るために後段に接続するのが一般的です。リードプレイには欠かせないアイテムです。
- Boss DDシリーズ (Digital Delay)
シリーズ
JCM900には、いくつかのバリエーションが存在します。
| モデルタイプ | 主なモデル名 | 特徴 |
| High Gain Dual Reverb | 4100 (100W), 4500 (50W) | チャンネルA/Bの2ch仕様。リバーブ搭載。フットスイッチでクリーン/リードの切り替えが可能で、最も人気の高いシリーズ。 |
| High Gain Master Volume | 2100 (100W), 2500 (50W) | 1チャンネル仕様。ゲインとマスターボリュームが2つあり、フットスイッチでマスターボリュームの切り替えが可能。リズム/ソロの音量差を作るのに便利。 |
| SL-X | 2100SL-X, 2500SL-X | “Super Lead X-tra Gain”の略。プリアンプの真空管を1本追加し、より強烈なハイゲインサウンドを追求したモデル。 |
| Studio JCM900 | 2900 (Head), 2901 (Combo) | 2024年に発表された20W/5W切り替え可能な小型モデル。オリジナルのサウンドを現代の自宅環境などでも扱いやすくしたリイシュー版。 |
JCM900の主なモデリング時の名称
JCM900は、その人気から多くのデジタルアンプシミュレーターやプロセッサーでモデリングされています。定番のMarshall 1960A/B + Celestion G12T-75のキャビネットと合わせて、代表的な名称を紹介します。
| プロセッサー | アンプのモデリング名 | キャビネットのモデリング名 (1960 + G12T-75) |
| Neural DSP Quad Cortex | Brit 900 | 412 UK C90 T75, GB 412 T75 |
| Fractal Audio (Axe-Fxなど) | Brit 900, JCM900 | 4×12 Brit 75W, 1960 T75 |
| Kemper Profiling Amplifier | “JCM900”, “Brit 900″等 | “1960” “G12T-75″等の名称を含むプロファイル/IR |
| Line 6 (Helix, PODなど) | Brit Gain 900, Brit J-900 | 4×12 UK T75, 4×12 Brit T75 |
| Boss (GTシリーズ, Katanaなど) | MS 1990 I/II | 4×12″ w/Celestion G12T-75 |
※上記は代表例であり、アップデート等により名称が変更・追加される場合があります。”Brit”, “UK”, “900”, “T75″といったキーワードが目印です。
JCM900の著名な使用者
JCM900は、特に90年代の音楽シーンにおいて、多くのアーティストのサウンドの核となりました。ここでは、長年愛用した、あるいは歴史的名盤でそのサウンドを刻んだアーティストを国内外で分けてご紹介します。
海外のアーティスト
- Noel Gallagher (Oasis)
90年代のブリットポップを定義したOasisのデビューアルバム『Definitely Maybe』やセカンド『(What’s the Story) Morning Glory?』で聴ける、あの壁のようなギターサウンドの多くはJCM900によって作られました。 - Billie Joe Armstrong (Green Day)
世界的な大ヒット作『Dookie』のサウンドは、改造されたMarshallアンプが核となっており、その中の一つがJCM900でした。90年代ポップパンクのサウンドを象徴する存在です。 - James Dean Bradfield (Manic Street Preachers)
デビューから長年にわたりJCM900の4100モデルを愛用。彼の情熱的でメロディアスなギターサウンドに欠かせない相棒として知られています。 - Dave Navarro (Jane’s Addiction, Red Hot Chili Peppers)
90年代を通じて彼のメインアンプの一つでした。オルタナティヴ・ロックシーンにおける、鋭くもサイケデリックな彼のギターサウンドを支えました。 - Jeff Beck
伝説のギタリストである彼も、90年代にはJCM900のDual Reverbモデルをツアーやレコーディングで多用し、その多彩な表現力の一端を担いました。
日本のアーティスト
- ken (L’Arc〜en〜Ciel)
90年代のL’Arc〜en〜Cielのサウンドを支えたアンプの一つ。特にアルバム『Tierra』『heavenly』期など、彼の独創的で美しいアルペジオからエッジの効いたリフまで、JCM900が貢献しました。 - SUGIZO (LUNA SEA)
メジャーデビュー初期のアルバム『IMAGE』や『EDEN』の頃、JCM900をメインに使用。彼の鋭利で空間的な初期のディストーションサウンドは、このアンプによって生み出されました。 - 横山健 (Hi-STANDARD)
日本のメロディック・パンクシーンを確立したHi-STANDARDにおいて、彼のスピーディーでパワフルなギターリフはJCM900から放たれていました。多くのキッズが彼のサウンドに憧れました。
JCM900はなぜ日本のどこのスタジオやライブハウスにある?
日本のスタジオやライブハウスに入ると、Roland JC-120と並んでJCM900が置いてある光景はもはや「お約束」です。それにはいくつかの明確な理由があります。
90年代の音楽シーンに完璧にマッチ
JCM900が発売された1990年は、日本が空前のバンドブームに沸いていた時代です。ハードロック、ヘヴィメタル、ヴィジュアル系、メロコアなど、「深く歪んだギターサウンド」がシーンの主流でした。JCM900は、特別な機材を追加しなくても単体で強い歪みが出せるため、当時の音楽シーンの要求にぴったりでした。
誰でも「良い音」が作りやすく高い汎用性
これがスタジオ機材として最も重要なポイントです。JCM900はマスターボリュームの効きが良く、比較的小さな音量でもバランスの取れた歪みが得られます。また、極端なクセがなく、どんなギターやエフェクターを繋いでも、ある程度の「マーシャルらしい良い音」にまとまるため、利用者を選ばないのです。
圧倒的に丈夫で壊れにくいから
不特定多数の人が、時にはラフに扱うスタジオ機材にとって、耐久性は生命線です。Marshall製品はもともとツアーなどの過酷な環境に耐えうる頑丈な作りをしていますが、JCM900もその例に漏れず、故障が少なく信頼性が高いことで知られています。
「定番」の地位確立と再生産
一度「JCM900とJC-120があれば間違いない」という「スタジオの常識」ができると、後からオープンするスタジオも、利用者に安心感を与えるためにまずこの2機種を導入します。この循環によって、定番としての地位が不動のものになりました。
まとめ
今回は、90年代のロックサウンドを定義した名機、Marshall JCM900を深掘りしました。純粋なチューブサウンドを求める声からは賛否がありつつも、その扱いやすさと時代が求めるハイゲインサウンドで、多くのギタリストを支えてきた一台です。
国やジャンルを超えて数々の名盤でその音を聴くことができるという事実がこのアンプの普遍的な魅力を物語っています。今なおリハーサルスタジオの定番として君臨し最新のデジタルモデリングの世界でもそのサウンドが再現され続けていることからも、その影響力の大きさがうかがえます。もしスタジオで見かけたら、ぜひ一度そのサウンドを体感してみてください。きっと、90年代の熱いロック魂を感じられるはずです。